「悪いのだけど、別れて欲しい。俺が愛しているのは、ラジルニーニャだけなのだ。君のように教養もない女性ではなく、賢くて強くて美しい完璧な女性なのだよ。ハハハッ」
久しぶりに帰って来た、金髪碧眼威圧夫スペードは、自宅のリビングで妻の私ダイアナ、夫の父クローバー、夫の母ハートにこう言い放った。
さすがに子供のサマンサとエドウィンは、部屋に戻していたが。
クローバーは怒りで顔を真っ赤に染めた。
「馬鹿者が! どれだけダイアナが、この家に尽くしたと思っているんだ。恥を知れ!」
ハートもそれに続く。
「そうですよ。子供達はどうするつもりなの?」
窘めるように、伝えてくれた。
それでも彼は堪えた様子はなく、「元々結婚が早すぎたんだよ。ダイアナは15才で嫁いできた。確かに可愛いかったけれど、それだけだろう? 碌に学ぶこともせずに公爵家に嫁いでも、ただ足を引っ張っただけだろう。社交さえ蔑ろにして」と、私を責め立てた。
本当に私は、こんな人が好きだったのだろうか?
私が何をしているかを、調べもせずに愚かだと言う。
確かに私は、外出を控えていた時期がある。
エドウィンが頻繁に熱を出していたからだ。
でもそれは子供が幼かった頃だけで、
二人が3才になる頃からは状態は落ちつき、社交界に復帰していた。
逆に何故知らないのだろう?
考えたくないけれど、私に興味がない、とか(泣)?
彼は結婚後、たがが外れてしまったように遊び歩くようになった。
結婚前はもう少し誠実で、律した様子もあったのに。
長女は13才、長男は10才。
後2年で、デビュタントが待っている。
そして今、公爵家の事業を切り盛りしているのは、この私だ。
義父母は申し訳ないと言う顔をして、私を泣きそうな顔で見ていた。
そんな顔をしなくても大丈夫ですわ。
覚悟は決めておりましたから。
「解りましたわ、旦那様。ただ1か月だけ時間を頂きたいのです。間違いなく出て行きますから」
真摯に伝えれば、夫も折れてくれた。
そこからダイアナ達の奮闘が、開始されたのだった。


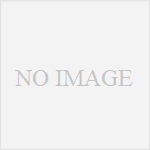
レビュー